こんにちは!
初心者さん応援!神戸トランペット吹きのクマガイナオコです。
このブログは、トランペット初心者の方やお悩みを持っている方が楽しくトランペットを吹けるようになるためのヒントになればと思って作りました(^^)
奏法からお手入れ方法までトランペットのあれこれをまとめていますので、気になることがある方は是非記事検索してみてください!
では、今日も記事を書いていきたいと思います。
今日は「チューナー」の使い方について。
早速解説していきましょう!

いつも使っているアイテムだから、効果的な使い方が知りたいなあ。
トランペット練習にあれば便利なものはこちらから!
チューナーとは
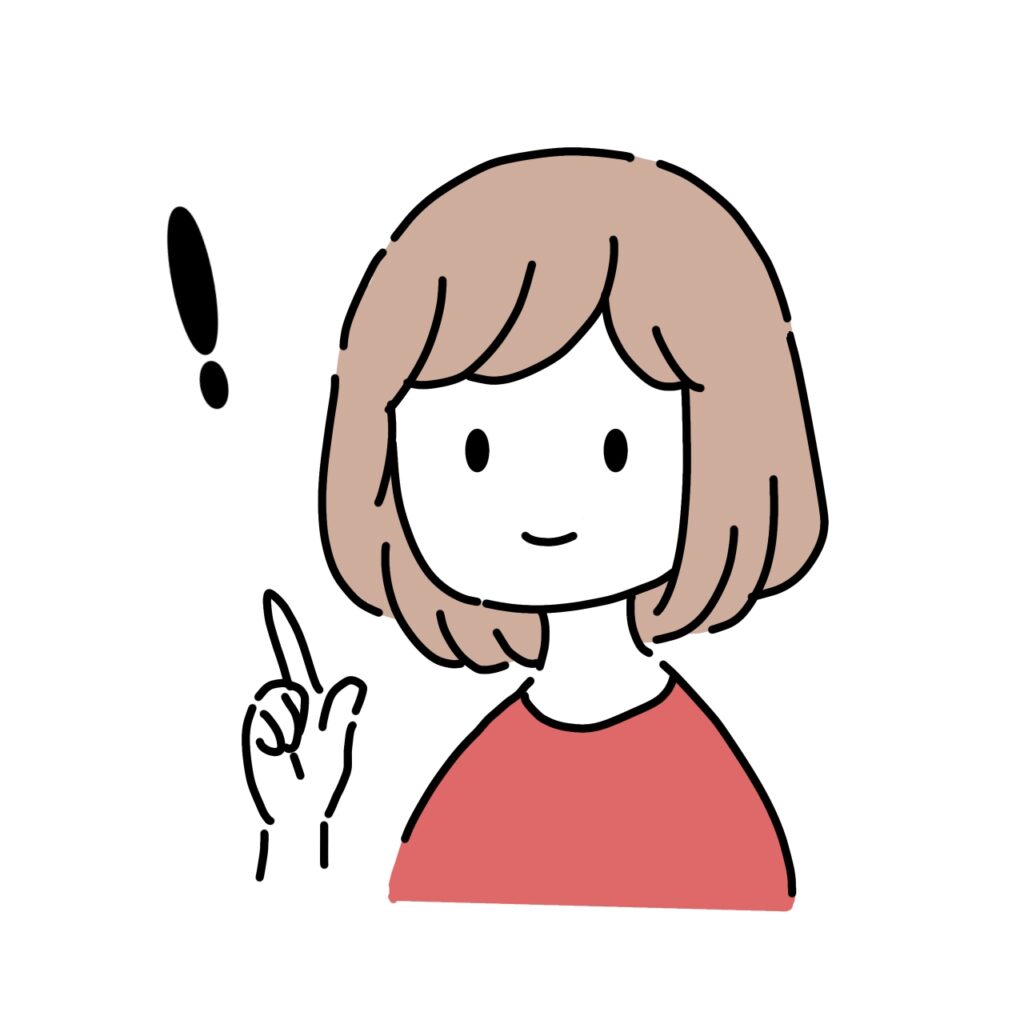
チューナーとは音程をはかる(チューニングする)機械のことです。
自分の出している音が基準の音より高いのか低いのかをメーターで表してくれます。
目で見てわかるので特に初心者さんの練習にあると便利なアイテムの一つです。
吹奏楽でトランペットを始めた方は特に、部活で始めに買い揃えるものの一つだったりするので、すでに持っている方も多いと思います。
便利なアイテムですが使い方を間違えるとあまり良くない習慣ができたりするので、是非最後まで読んで効果的に練習に役立ててくださいね。
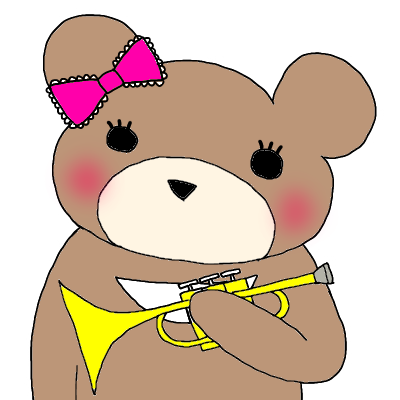
効果的な練習ができるようにしたいわね。
チューナーの操作方法
周波数の設定

まずは周波数(Hz=ヘルツ)を設定します。
チューナーによって違いはありますが、画面のどこかに3桁の数字があると思います。
上の写真で言うと左上にある数字です。
その数字を442Hzに設定しましょう。
日本の吹奏楽では、基準は442のところが多いです。
ギターやベースなどの弦楽器は440でチューニングされるようなので、一緒に演奏する楽器によっても変わってくる部分ですが、ひとまず管楽器の一般的な442にしておきましょう。

「基準がずれていた」なんてことのないようにしっかり442Hzに合わせておこうね。
メーターの見方
設定ができたら、早速メーターの見方を覚えましょう。
チューナーをベルの先に置き、音を鳴らします。
マイク付きのチューナーの場合は見やすい主管、もしくはベルの先にマイクを挟み音を鳴らします。
音を吹いている間はメーターが左や右に動きます。
左が低く、右が高い表示です。
安定して吹けているとメーターが大体同じ位置で止まって見えます。
できるだけ真ん中に近いところでメーターが留まるようであれば、良い音程で安定して吹けていると言えます。
真ん中だけ緑色に光るチューナーもありますね。
ただ、人間は機械ではないので、メーターが完全に止まるように吹くことはできません。
機械だけを見て判断するのではなく、あくまでも参考程度に使うことをオススメします。
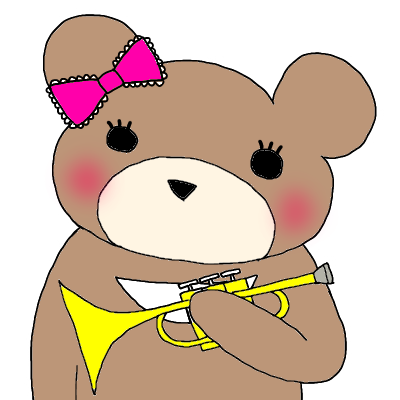
最終的な判断は自分の耳でできるようになるのが良いわね。
音名表示
チューナーには自分の出している音がアルファベットで表示されています。
そちらも合っているかを確認しましょう。

こちらの画像で言うと左端にあるAという表示です。
Aはトランペットでいうシの音です。
自分がシを吹いている時にちゃんとAになっていることを確認します。
音程が高すぎたり低すぎたりすると隣の音の表示が出るので、しっかりその音の範囲に収まるように気をつけましょう。
アルファベットの音名についてはこちらの記事をご覧ください。
音が出るチューナーも
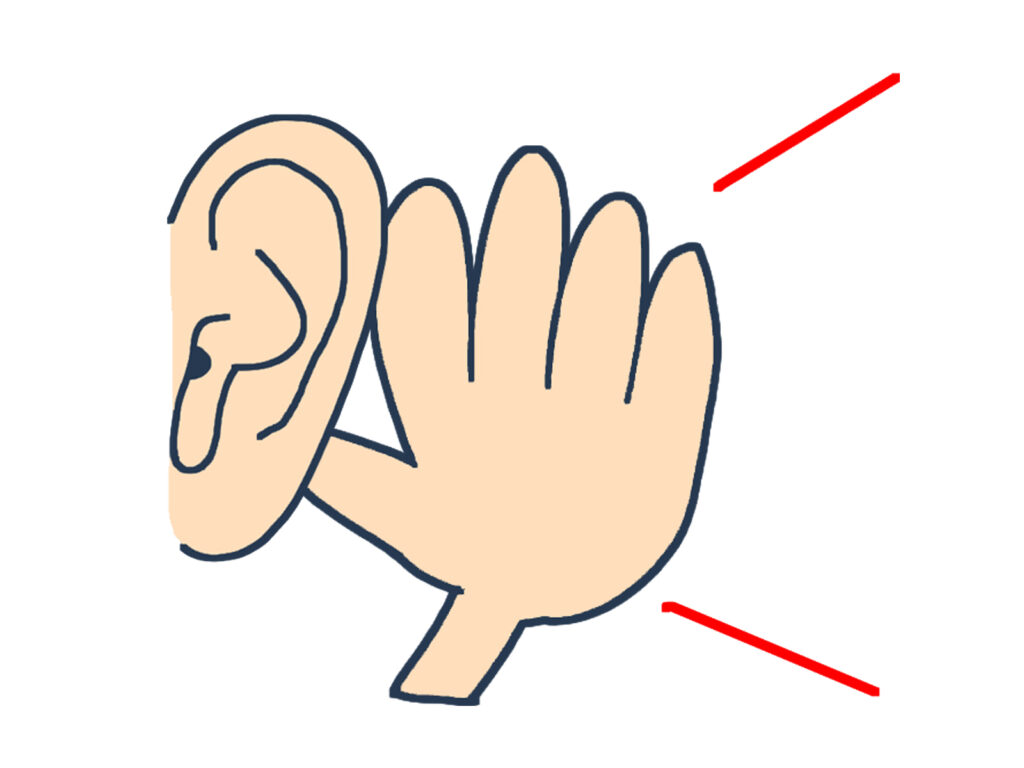
チューナーの中には音を鳴らすことができるものもあります。
1オクターブ分の音階が順番に鳴らせるようになっていて、ちょっとした音程確認にとても便利です。
こちらも音名がアルファベットで表示されるので、アルファベットの音名を覚えておくと良いでしょう。

トランペットは移調楽器だから、他の楽器と合わせるときにはアルファベットの音名(またはドイツ音名)が役立つよ!
メトロノームつきやクリップ式も
メトロノームつきの便利なものもあります。
練習に必要なものが一つにまとまっているので持ち運びにも便利ですね。
クリップ式のチューナーもあり、小型でコンパクトなので使いやすいものを選ぶといいですね。
大勢で吹くことが多い方はマイクがあると便利です。
自分の音だけをしっかり収音してくれます。コードが断線しやすいのでお取り扱いにはご注意くださいね。
基本的な使い方

操作方法がわかったところで、基本的な使い方を紹介します。
メーターの見方のところでもやったようにベルの先にチューナーをおきます。
譜面台がある方は譜面台が良いでしょう。
できれば楽器は両手で持って吹きたいので良い場所を探してみてください。
マイクつきやクリップ式の方は主管やベルにつけます。
吹きたい音をイメージして、リラックスして音を伸ばします。
初めは音に集中したいのでチューナーは見ません。
吹いてしばらくしてからチューナーをチェックします。
メーターが左にあるようであれば低く、右にあるようであれば高いです。
チューニング管を調整しましょう。
低い時は入れる、高い時は抜きます。
自分が楽に吹いた状態で大体真ん中にくるようにチューニング管の調整ができたら完了です。
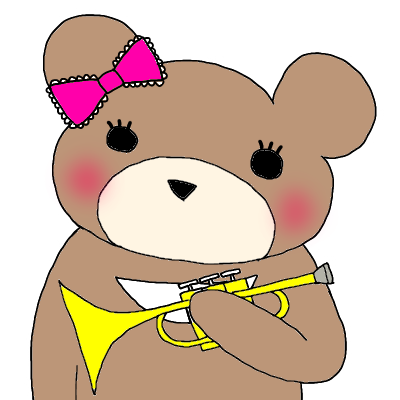
ポイントは自分のいい音で吹くことと、初めからチューナーを見ないことね!
気温が低いと音程も低くなり、気温が高いと音程も高くなります。
できるだけ人間にとっての適温で練習するのが好ましいですが、野外で演奏する場合などは気温も考慮してチューニングすると良いですよ。
ちなみに、吹き方によって低くなったり高くなったりしやすい方もいらっしゃいます。
チューニング管は1cm程度抜いた状態が楽器の状態が一番良いと言われています。
大幅に抜いたり入れたりしないと合わない場合は、無理のない奏法で吹けているかをチェックしてみるのがおすすめですよ。
こちらの記事で口周りの練習ができるので気になる方は試してみてください。
私のオススメ チューナーの使い方
初心者さん向け

レッスンを経験してきて、初心者さんは自分が今何の音を吹いているのかわからないという方がとても多かったです。
そんなときにチューナーを使ってみましょう。
吹いた後にチューナーに目をやります。
そのとき表示されている音名を見て、高さを覚えましょう。
何度も繰り返しているうちに、この高さはこの音だな?という感覚が掴めるようになっていきますよ。
慣れてきたり、吹いている音はわかるよという方は次の項目を見てみてください。

初めは分からなくても大丈夫だよ。
使えるアイテムを上手に使って身につけていきたいね。
中級者さん向け

そもそも音程は自分の持っている音程感が非常に重要で、頭の中でいい音程で歌えているかが吹く音にも表れてしまうのです。
なので、中級者さんはチューナーで音を鳴らして聞き取ってから吹く練習をしてみてください。
繰り返すうちに良い音程が聞かなくても自分の頭の中でイメージできるようになりますよ。
ではまずチューナーで音を鳴らします。わかりやすくドの音=B♭にしましょう。
しっかり聴いて、実際に鼻歌で歌ってみたり、頭の中でその音を一緒に歌ってみたりします。
十分にイメージできたらその音を実際にトランペットで吹いてみましょう。
吹いてから数秒後、チューナーで音程をチェックしてみましょう。
慣れてくればある程度真ん中を狙って吹けるようになっていきます。
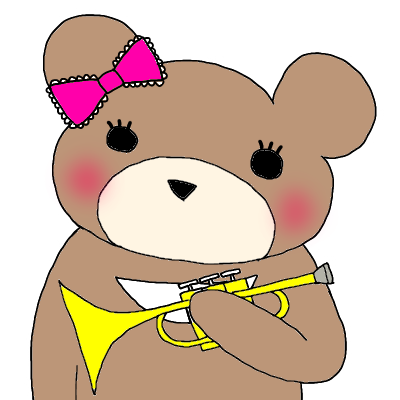
いい音程が頭にあれば曲を吹くときにも活かせるわ
終わりに
記事の中でもお伝えしましたがチューナーはあくまでも機械です。
ずっと機械に頼る練習をしてしまっては、せっかくあなたの持っている音感やイメージが育たず衰退してしまいます。
効果的に使ってトランペットが楽しく吹けるようにしてみましょう。
応援しています(^^)
ブログ更新のお知らせは、LINEのお友達登録で受け取ることが可能です♪
お友達限定で楽器の洗い方・基礎練習の楽譜をダウンロードプレゼント中です(^^)
是非登録してくださいね!
また、生徒さまも募集中です!
気になる奏法やステップアップのコツなど、一人一人に合わせたスピードでアドバイスしています。
ご希望の方がいらっしゃいましたら、簡単なフォーム入力でお問い合わせできます。
是非こちらよりお問い合わせください!
レッスン詳細はこちら(^^)

クマガイナオコのホームページはこちら↓
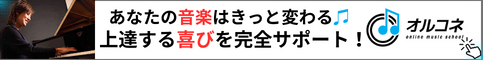


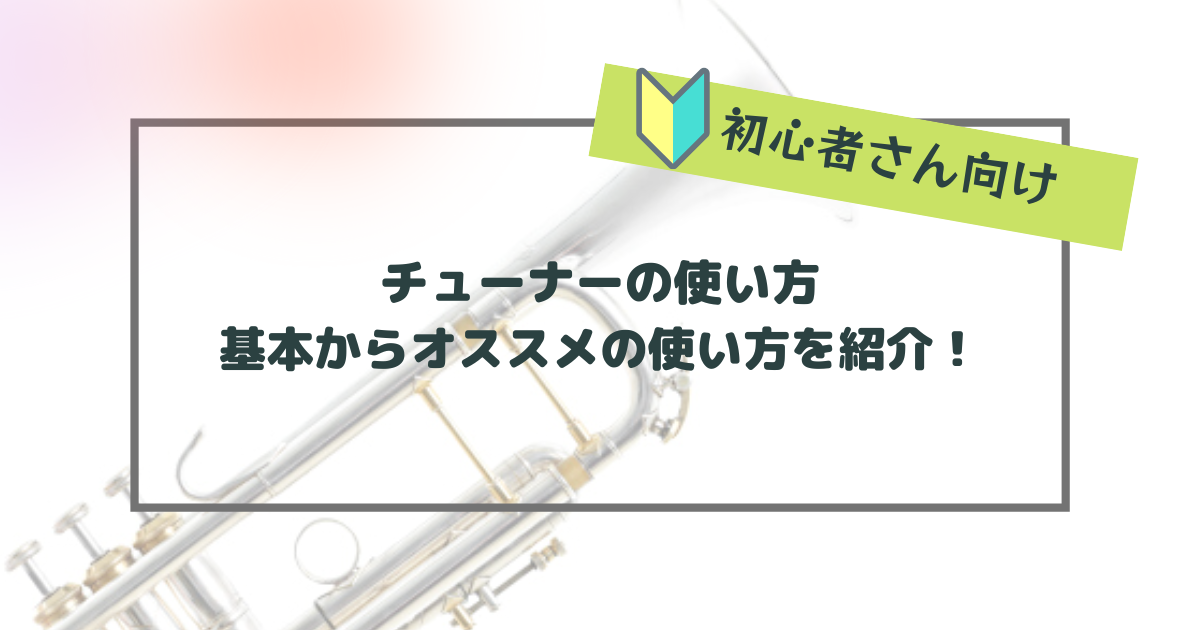
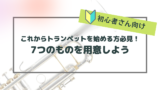
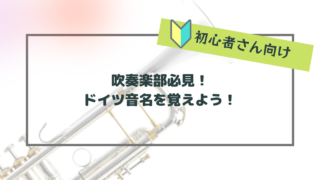
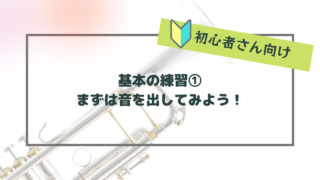

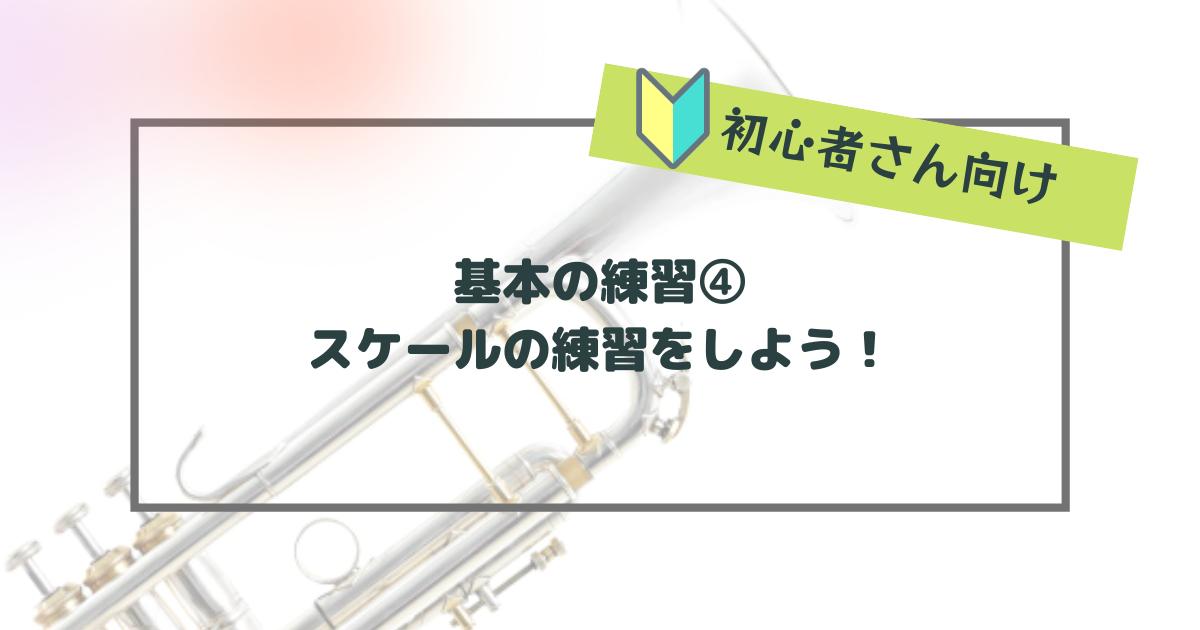
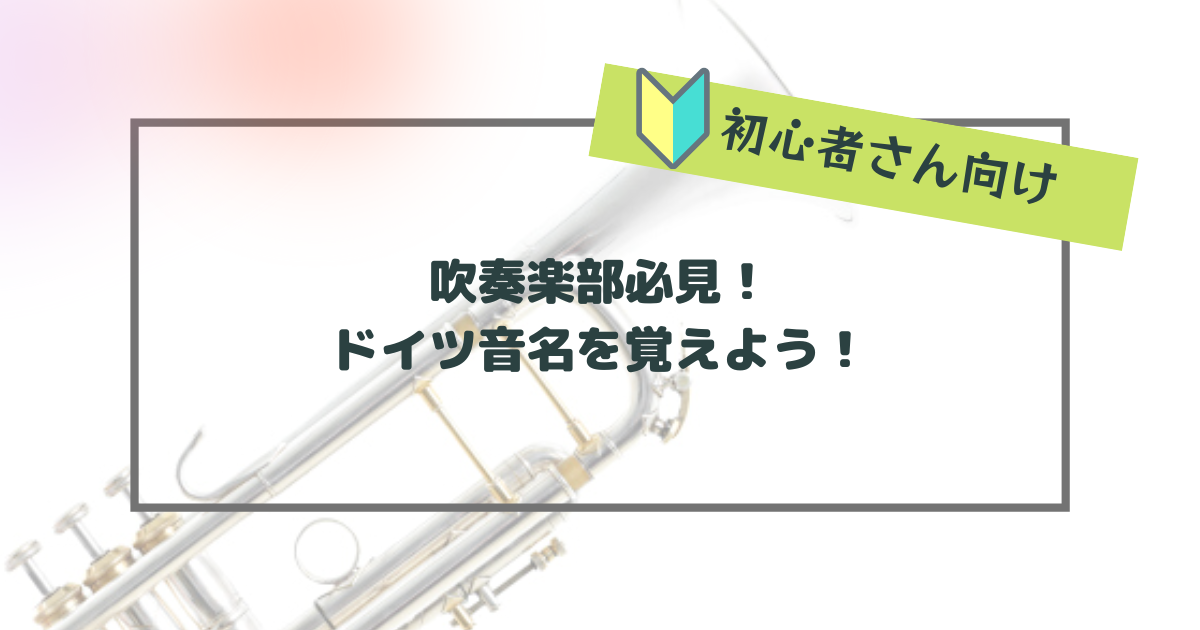
コメント